言葉のモヤモヤを云々します。音楽理論の話はしません(笑
グルーヴと漢語と和語
「ジェントルでタイトなグルーヴが…」何気なく人への便りに書いた。
片仮名ばかりで鼻につくかと逡巡、。
「優麗かつ厳格な…」いやいや、これまたやりすぎだろう。
漢語の集中的連発はキツい。
ココで気づく。
「グルーヴ」は漢語に訳すと
「律動」、、、ではないのだろう。
それは「リズム」を和訳するのに作られた明治時代の和製漢語(と筆者は思ってる、要取材)。
で、リズムとグルーヴって言葉を「違うもの」と我々は少なからず受け止めてるはず。
その違いを反映した適確な漢語を過去に聞いたことががない。
強いて作ってみると、、、
「不可二或三分割規則厳格永久連綿不変形波動其与我快感」
か、、ねぇ~~よ(笑
和語にしてみる。
「たおやかでたわまぬ…」
やはりグルーヴに相当する和語を思いつかない。
つまり、日本語の歴史にグルーヴにあたる言葉は生まれてこなかった、だから片仮名表記でしかない、ってことなのでしょう。
強いて言えば「ノリ」「のってるね~!」ってのが近い表現。
たぶん第二次大戦終戦以降に、音楽が引き起こす感情を表す言葉として作られたものなのでしょう。
大橋巨泉さん以前にあったか否かは興味深いので要取材。
グルーヴとアゴーギクとリズム
時間のモノサシとして等間隔の目盛りを聞かせてくるのがメトロノーム。
目盛りの「幅=経過時間」がテンポ。
ゾロリと並ぶ目盛りに、周期的に長短(or 濃淡)を描き、それを音圧や音色などの変化に対応させる。
するとそこにリズムが生まれる。
時間軸上での「同じ出来事の繰り返し」の感覚を人に与えるってこと。
つまりそれは「拍子」。
メトロノームは
・等間隔の目盛り
・その幾つかをグルーピングした濃淡の繰り返し
だけでなく、
・上記目盛りを2分割 or 3分割した小さな目盛り
も示す。
そこまでが基本性能。
で、どの目盛りも「等間隔」なのが特徴。
西洋クラシック音楽では、時間軸上の情報はメトロノームの目盛りで「おおかた」説明がつく。
時に、
・テンポを変えたり、
・等間隔な目盛りに「ゆらぎ」を与えたり、
といった「不規則な」(←ここ重要!)出来事を起こすのを「アゴーギク=速度法」と呼ぶ。
・基本的な目盛りの位置(時間の進み方)は変えずに揺らぐこと(↑の後者)
もあれば、
・目盛りの位置自体を変更すること(↑の前者)
もあるってわけ。
なわけで、クラシック音楽の説明では、テンポとリズムで「おおかた」事足りて、グルーヴって言葉は登場しないのでしょう。
ですが!
ワルツとかメヌエットとか「ダンスありき」のスタイルでは、
「目盛りが等間隔ではない。だがそれは、ソノカタチを厳密に繰り返す」
ってものもあるし、そのタイプのものは、
「テンポの変化を嫌う」
です。
それって正にグルーヴだなと筆者は理解してます。
グルーヴとシャーマニズムとダンス
時間軸上での出来事の精確な繰り返しに触れると人間は、なにかしら精神作用を引き起こされるらしい。
それは日常生活での感覚とは違う、陶酔といった類のものと言えましょう。
太古の時代よりシャーマン(霊媒師、神降ろし…)には打楽器がつきものだったのも解りやすい。
あれは神や霊をそこに降ろすためではなく、オーディエンスの陶酔を呼び、日常的判断を失わせた、わけですな。
そこに身体の「繰り返し動作」を乗せて、陶酔作用を更に深めてくのがダンス。
ダンスの原初はきっとそうなのでしょう。
現在では、装飾的動作を表象的に多様して、それを視覚的にアートとして愉しむものとなってるわけですね。
でですね!
「時間軸上での出来事の繰り返し」は、
本当に「精確に」行われてこそ精神作用を喚起するものらしいです。
で、
そこに起こる出来事は、メトロノームの目盛りのような「等間隔で、2 or 3の倍数で整理される」ってことでなくてよい。
メトの目盛りからはズレたとこにある出来事でも、それが「精確に繰り返される」ならば、精神作用を引き起こす材料になる。
それがグルーヴなんだと筆者は理解してます。
、、、なので
「不規則な揺らぎ」をグルーヴだって説明を見かけるとお腹がキュルキュルってなります(笑
グルーヴとアメリカ音楽
黒い人達がアフリカの西海岸から、白い人達に無理矢理に新大陸に連れてこられ、綿花栽培労働を強制された。
人が動くと文化も地理的に移動する。
違う文化の人が出会うと、影響し合った新たな文化が生まれる。
黒い人達の持ってた、自然倍音列の聴き分けから生まれたハーモニーと音階の感覚(筆者長年の研究テーマ、沢山まだ要取材)と、西洋の平均律(ほぼ。まだ過渡期的な)で調律された楽器とが出会って、その衝突的解決努力から生まれたのがブルーズ(と筆者は思ってる)。
黒い人達のダンス・太鼓文化・発語リズム・歩き方…と西洋のリズム概念が出会って生まれたのが、
・ステディー(規則的)なビート(打突)を繰り返して「こそ」始まる音楽
・西洋のアウフタクトとは違った趣のフレージングのアタリマエ
…つまり新たなリズム感、なのでしょう。
それら特徴を持った「アメリカ音楽」は、強大なる資本主義を背景に、蓄音機・ラジオ放送・楽器産業をメディアとして世界を席巻してったわけですね。
新たなリズム感は、メトロノームの目盛りでは測れない、より微細な目盛り(=グルーヴの材料)の存在をもアタリマエにしました。
つまりそこにグルーヴって言葉が、
グルーヴあらばこその音楽的現象を説明するため
に使われ始めたのでしょう。
グルーヴ groove 、ノってるねい!
もともと、溝_ミゾ とかって意味の古くからある普通の言葉。
あ、「ハマる」って言いますよね。
それって「ミゾにピッタリとフィットしてる」ってこと。
昭和の言葉感覚で言うとこの
「波にうまくノってる」
と同じですね。
音楽の生み出す波に、ひとの心の波がピタリと一致した時。
それを「ノってる」「ハマってる」「グルーヴしてるねい」
と表現するわけですね。
つまり、音楽に
・生み出そうとしてそこに生まれた出来事
だけでなく、
・それを感受した人の状態
をも
グルーヴって言葉は意味として含んでますね。
それはリズムやテンポにはない言葉感覚です。
農耕民族と狩猟民族、、ってかさ、、
こういう話になるとさ、すぐ語られるのがさ、安易にさ、、、
「日本人は農耕民族で、西洋人は狩猟民族で、、」
って話。
田植えをしたか馬に乗ったかってね。
あのさ、まずね、現象観察としてもさ、
この島の音楽にもグルーヴィーなものは沢山あるわけさ。
日本語、それ自体がテンポステディに2拍子系のリズムで発語されるものだしね。
小さな島だけど太古は複雑な多民族国家だったとしか思えないし。
多様な文化の痕跡は各地に残ってるし。
まずさ、「○○は黒か白だ」って話はさ、その段階で眉唾だって感じてます。
その件、本論とはさほど関係無いんで、これくらいにしといてやろう。
ま、グルーヴ万歳!ってことですわ。
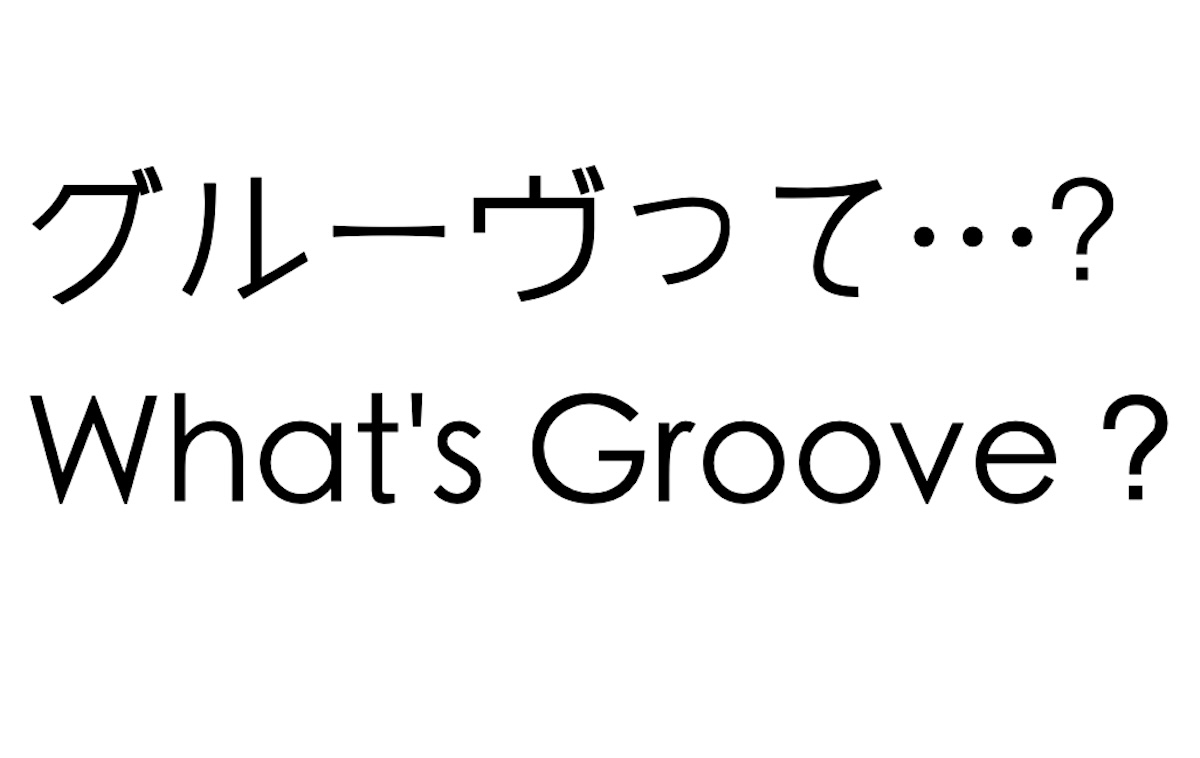
コメント